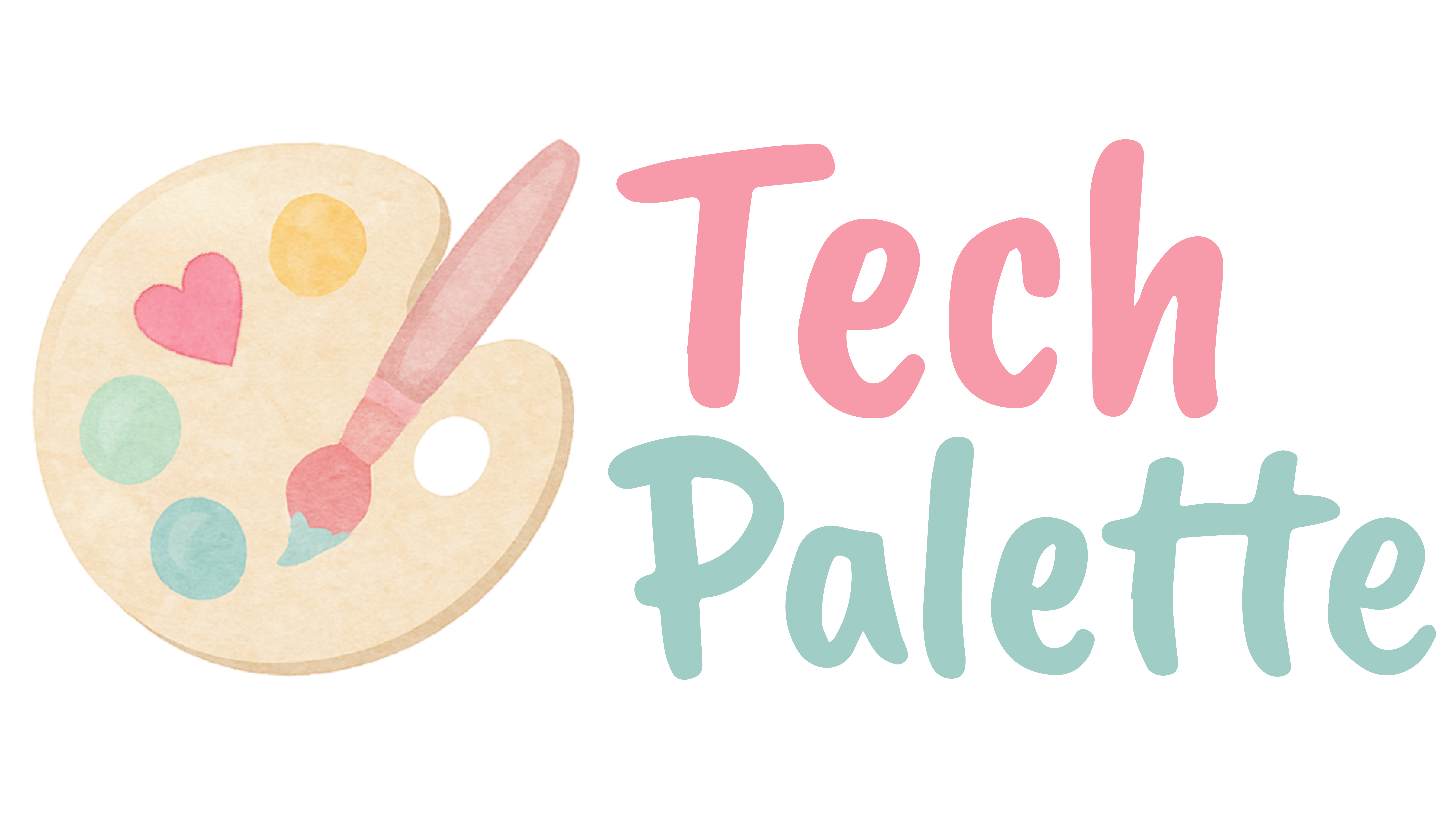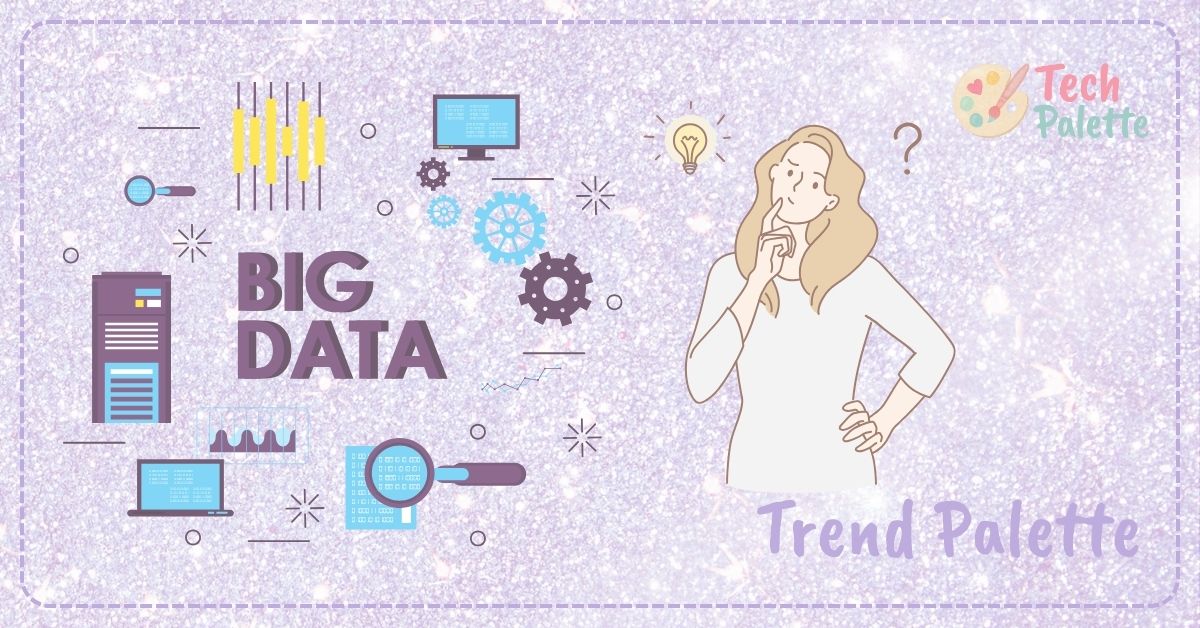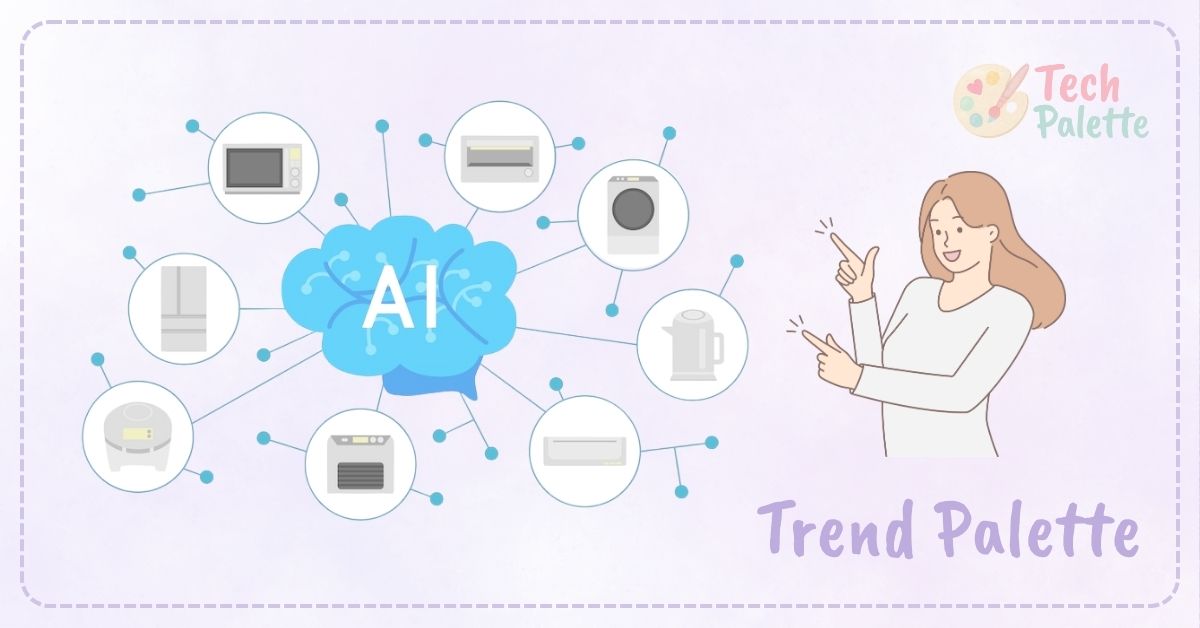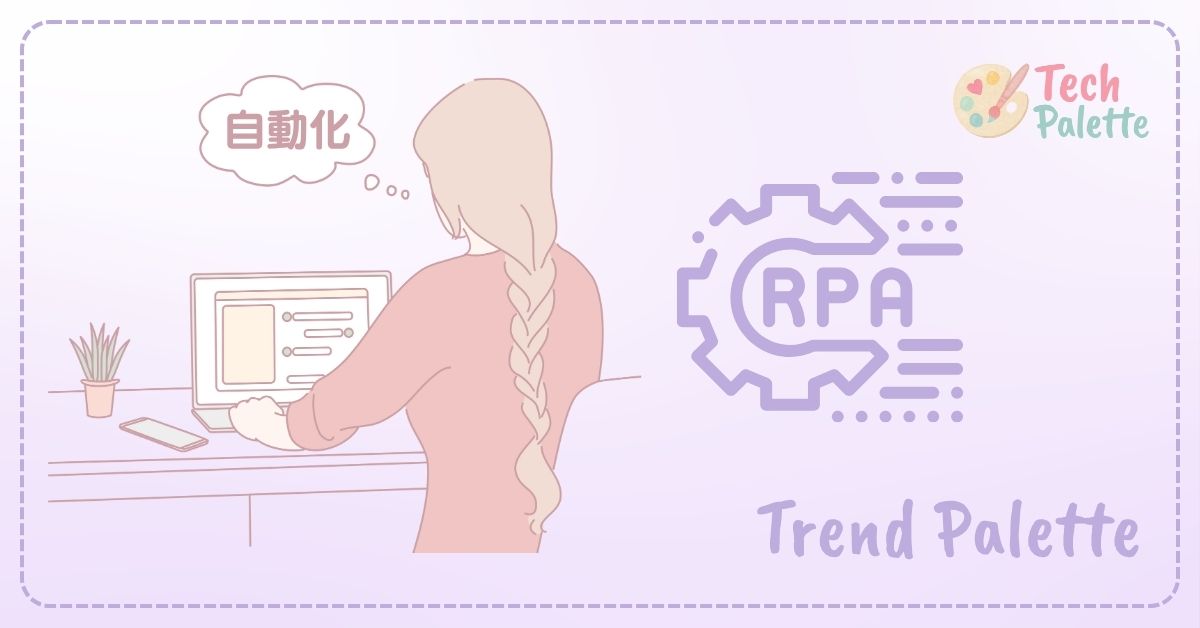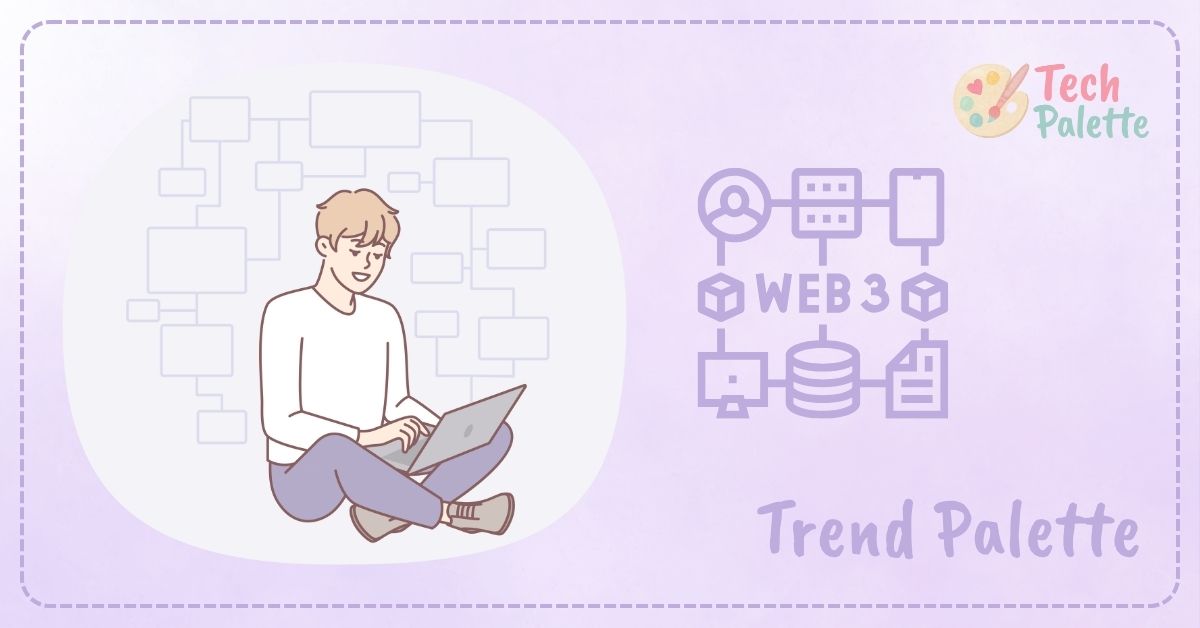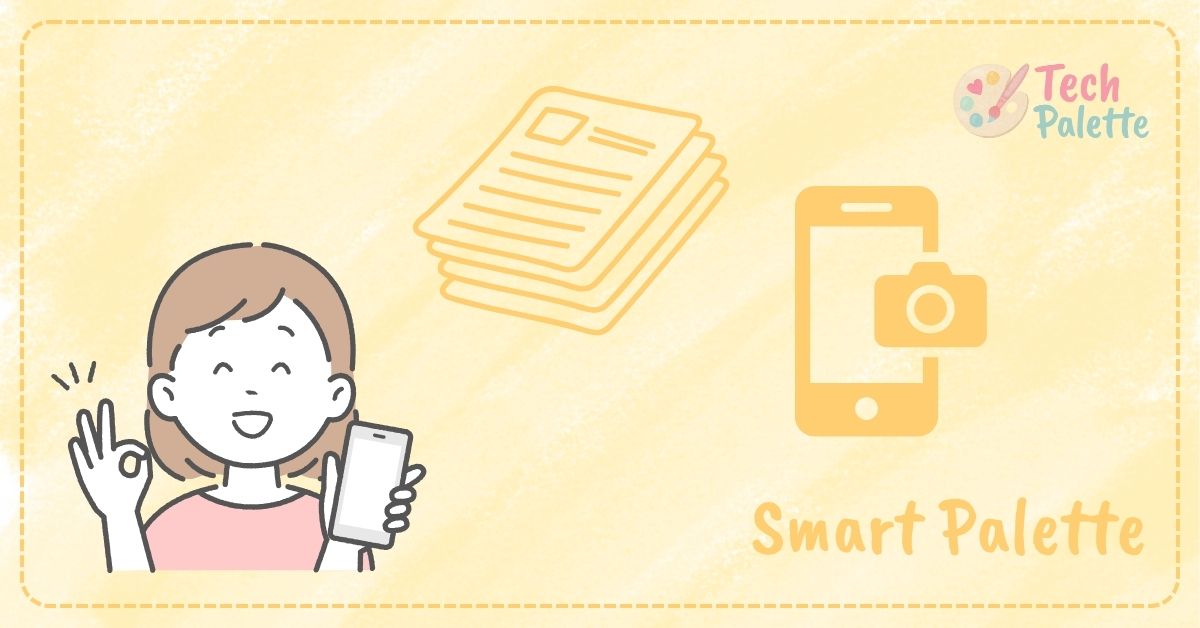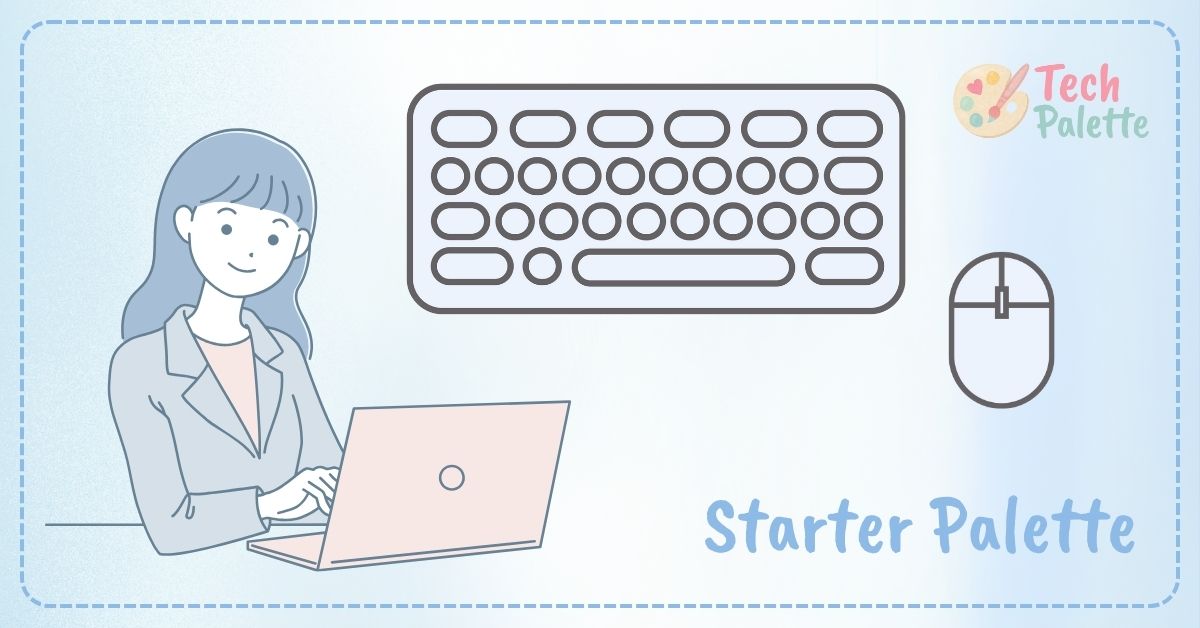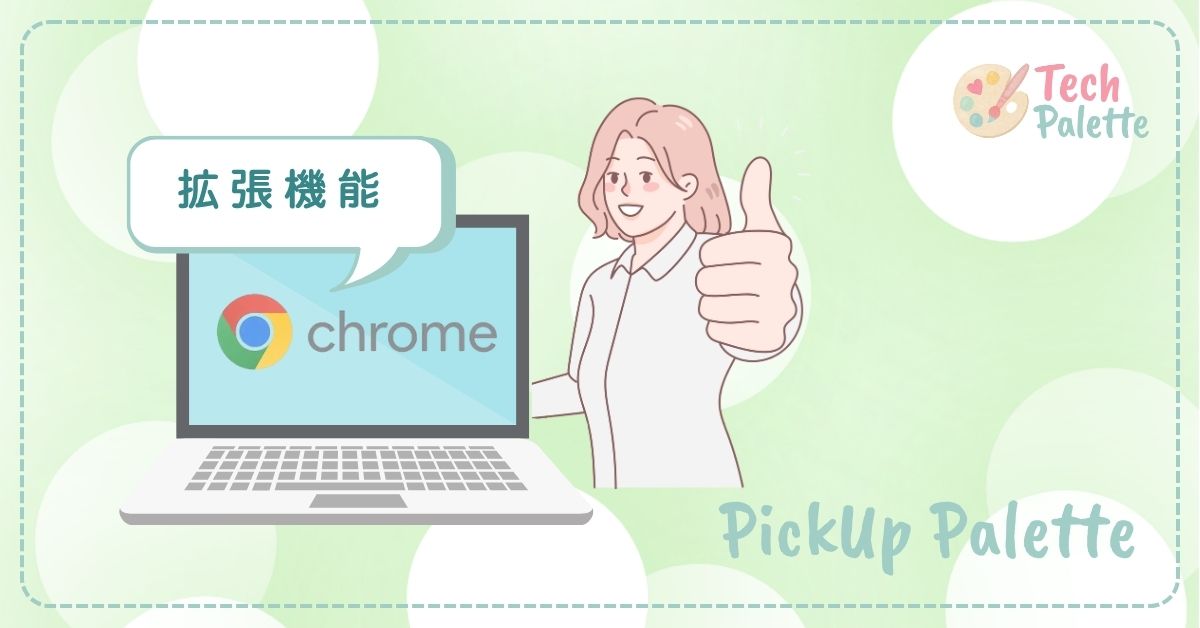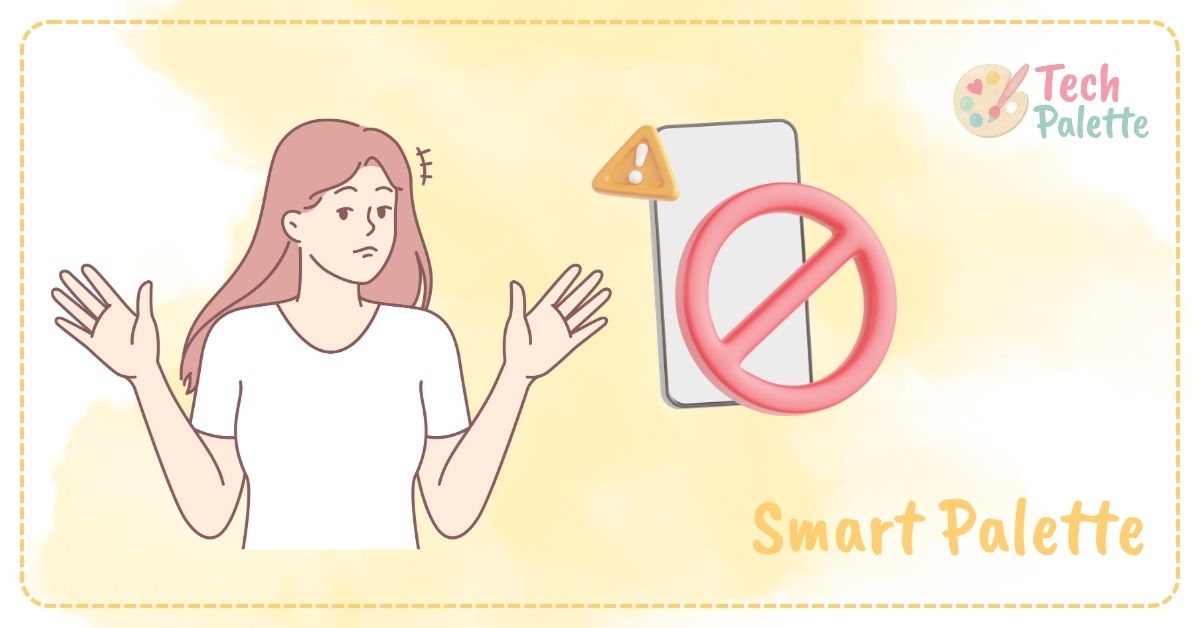デジタルウェルビーイングとは?心地よいテクノロジー活用術
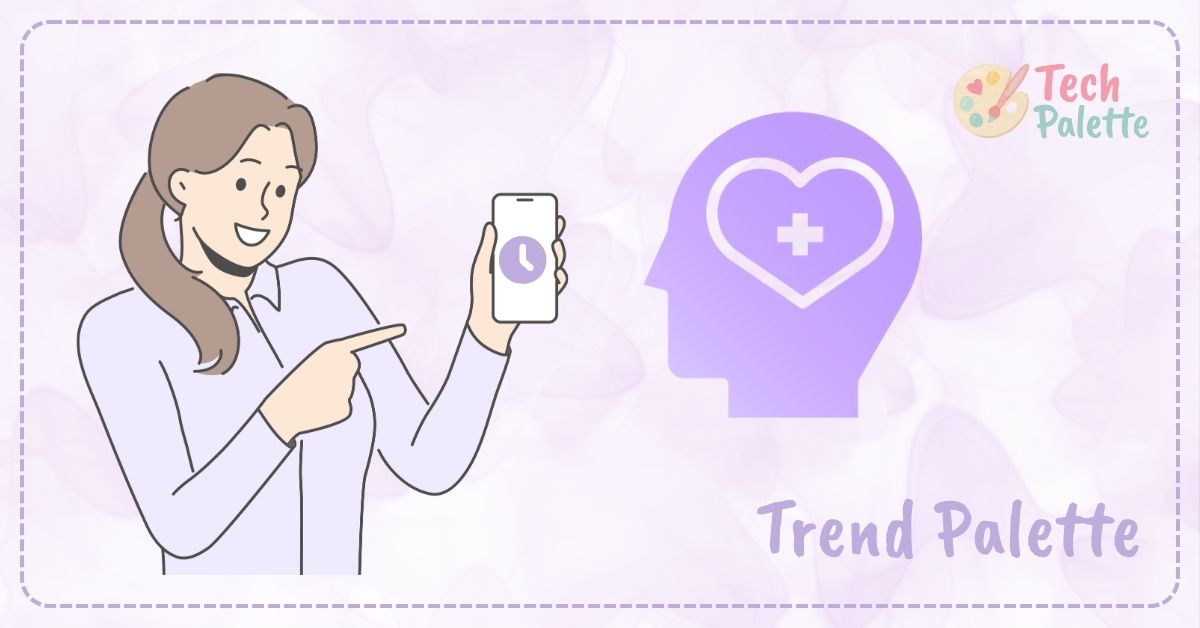
なぜ今「デジタルウェルビーイング」が必要なのか
日々DX推進やシステム業務に携わるなかで、テクノロジーが私たちの暮らしや仕事に深く根付いていることを実感しています。
ChatGPTやCanva、Google Workspaceなどの便利なツールは、業務効率を大きく高め、働き方を柔軟にしてくれました。
一方で、「テクノロジーに振り回されているかも」と感じた経験はありませんか?
スマートフォンが手放せず、通知が気になって落ち着かない。
そんな“情報疲れ”を、私自身も感じることがあります。
こうした現代的な悩みを受けて注目されているのが、「デジタルウェルビーイング」という考え方です。
本記事では、「デジタルウェルビーイング」の意味や重要性、そして実際に私が試して効果を感じた実践法をご紹介します。
デジタルウェルビーイングとは?テクノロジーと心地よくつながる方法
デジタルウェルビーイング(Digital Wellbeing)とは、テクノロジーを意識的・健康的に活用し、心身の健やかさを保つ状態を指します。
スマホやPC、SNSはとても便利ですが、使い方を間違えると、ストレスや集中力低下を引き起こすこともあります。
GoogleやAppleもこの課題に注目し、使用時間の管理機能を搭載。
「テクノロジーを敵視するのではなく、味方として上手に共存する」というのが、デジタルウェルビーイングの基本的な考え方です。
デジタルデトックス(意図的に機器から離れる)とは異なり、日常的にテクノロジーとのバランスを取る習慣をつくるのが特徴です。
関連記事:スマホの通知に疲れたあなたへ。デジタルデトックスのための設定術
広がるデジタルウェルビーイングの取り組み
日本でもデジタルウェルビーイングの概念が広まりつつあり、2020年には「一般社団法人日本デジタルウェルビーイング協会(JDWA)」が設立されました。
▶ 一般社団法人日本デジタルウェルビーイング協会(JDWA)
JDWAは、「テクノロジーによって人生を豊かにする」を理念に、教育や啓発活動を展開しています。
この協会が提唱している「Digital Healthy(デジタル・ヘルシー)」というキーワードは、心身のバランスを保ちながら、テクノロジーと付き合うための指標として、多くの人に受け入れられ始めています。
社会全体で、テクノロジーとの関係性を見直す動きが広がっているのは、誰もが「このままでいいのかな?」という小さな違和感を感じている証拠なのかもしれません。
あなたは大丈夫?テクノロジー依存のサインとは
「なんとなくスマホを触ってしまう」
「SNSを見て疲れてしまう」
そんな違和感があるなら、テクノロジーとの関係を見直すタイミングかもしれません。
スマホ依存度チェックリスト
当てはまる項目が3つ以上あれば要注意です。
- スマートフォンが手元にないと不安になる
- 起きてすぐや寝る直前にスマホをチェックしている
- 通知が気になって仕事や家事に集中できない
- 食事中や会話中もスマホを無意識に見てしまう
- 使用時間が思っていたよりも長くなっている
- 充電残量が少ないと不安になる
- 通知がないか、頻繁に画面を確認してしまう
- 睡眠時間がスマホのせいで減っている
- リアルの交流よりSNSを優先することがある
- スマホをやめたいと思いつつもやめられない
見逃しがちな心と身体のサイン
- 通知疲れ — ひっきりなしの通知で気が休まらない
- 情報過多 — SNSやニュースで必要以上の情報にさらされ疲弊する
- 集中力の低下 — 細かい通知や誘惑で注意が散りがち
- 睡眠の質の低下 — 就寝前のスマホ操作で寝つきが悪くなる
- 眼精疲労・肩こり — 長時間の画面操作による身体的な負担
- SNSでの比較による自己肯定感の低下
私自身も、SNSからの情報で気持ちが沈んだり、何を信じたらいいのか分からなくなる経験をしました。
まずは、自分の今の状態に気づくことが、改善への第一歩です。
デジタルウェルビーイングを高める4つのステップ
1.自分の使用状況を「見える化」しよう
まずは、スマートフォンの使用時間をチェックしましょう。
iPhoneなら「スクリーンタイム」、Androidでは「デジタルウェルビーイング」機能が役立ちます。
「なぜこのアプリを使うのか」
「本当に必要な機能なのか」を考えるだけでも、利用の仕方が変わってきます。
おすすめは、小さな目標を設定すること。
たとえば「寝る1時間前はスマホを触らない」と決めるだけでも効果があります。
私もこの習慣で、読書やストレッチの時間が増え、睡眠の質が向上しました。
2.スマホの設定を見直して“負担”を減らす
- 不要な通知はオフに設定
- グレースケール表示で視覚刺激を減らす
- 集中モードやおやすみモードを活用
- よく使うアプリをホーム画面から移動する
- アプリごとの利用制限を設定する
私は仕事用の一部ツールを除き、通知はほぼすべてオフにしています。
それだけで、心の余白がぐんと広がりました。
3.意識的な「ノーデジタル時間」をつくる
- 食事中や入浴前後はスマホを触らない
- 休日や旅行中にスマホの電源をオフにする
- スマホを持たずに近所へ散歩する
はじめは不安でも、徐々に“スマホのない時間”の快適さに気づけるようになります。
私も、スマホをかばんに入れたまま出かけるようになってから、家族との時間や景色を楽しむ余裕が生まれました。
4.テクノロジーを「わたしらしく」活用する
デジタルウェルビーイングは、テクノロジーを遠ざけることではありません。
むしろ、うまく味方につけるための工夫です。
- アプリを目的をもって使う
- 学びや創造につなげる(例 — WordPressやCanva)
- 信頼できる情報源だけを厳選する
- オンラインの知識をオフラインで実践する
私にとって、テクノロジーは「難しそうなもの」から「自分らしさを広げる道具」へと変わりました。
そんな気づきを、少しでも多くの方と共有したいと思っています。
おすすめ書籍の紹介
『DIGITAL STANCE スマホに支配されない生き方
−テクノロジーとの「健全な距離感」を見つける−』
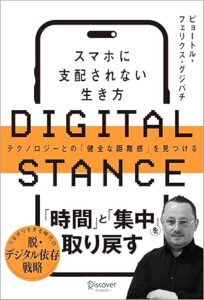
出版社:ディスカヴァー・トゥエンティワン
著者:ピョートル・フェリクス・グジバチ
テクノロジーに振り回されず、自分らしい“使い方”を選ぶ視点を与えてくれる一冊です。
著者は、Googleで人材育成を担当していた経験を持ち、アテンションエコノミーの仕組みを深く理解しています。
“やめる”ではなく、“距離を整える”。
スマホ時代の私たちにぴったりのヒントが詰まっています。
おすすめポイント:
- 「スマホ疲れ」は意志の弱さではない
テック企業が意図的に設計した“ハマる仕組み”に対し、冷静に気づける構成です。自分を責める前に読むべき一冊です。 - 「選ぶ」「整える」「距離をとる」という実践的アプローチ
すぐに実行できる視点やマインドセットが紹介されており、誰でも少しずつ生活を変えていけます。 - あらゆる立場の人に向けた巻末ガイド
ビジネスパーソンから学生、保護者、クリエイターまで。自分の立場に合わせたヒントが見つかります。
スマートフォンとの付き合い方に悩んでいる人や、「なんとなくモヤモヤする」感覚を抱えている人にとって、この本は、自分自身とテクノロジーとの関係を見つめ直す大きなきっかけになります。
「使われる」から「使いこなす」へ。
あなたの“デジタルスタンス”を整えるヒントを、ぜひこの一冊から見つけてみてください。
▶ 【Amazon】でくわしく見る
▶ 【楽天ブックス】でくわしく見る
【まとめ】テクノロジーとの付き合い方は自分で選べる
テクノロジーは、生活を便利にし、学びの可能性を広げてくれる強力なツールです。
しかし、付き合い方を誤ると、心や体の不調にもつながります。
「自分にとってちょうどよい距離感」を見つけることが、デジタルウェルビーイングの本質です。
- 使用状況の見える化と小さな目標設定
- 通知や画面設定の見直し
- スマホを手放す時間の確保
- テクノロジーの目的意識を明確にする
これらを実践することで、テクノロジーに振り回される毎日から解放され、自分らしい時間や働き方が見えてきます。
このブログ「Tech Palette」は、「テクノロジーを、わたしらしく。」をテーマに、あなたの暮らしや仕事に役立つツールや考え方をお届けしています。
「わたしにもできた」その小さな実感が、あなたの未来をやさしく後押しできますように。
▶ 一般社団法人日本デジタルウェルビーイング協会(JDWA)
関連記事:スマホの通知に疲れたあなたへ。デジタルデトックスのための設定術