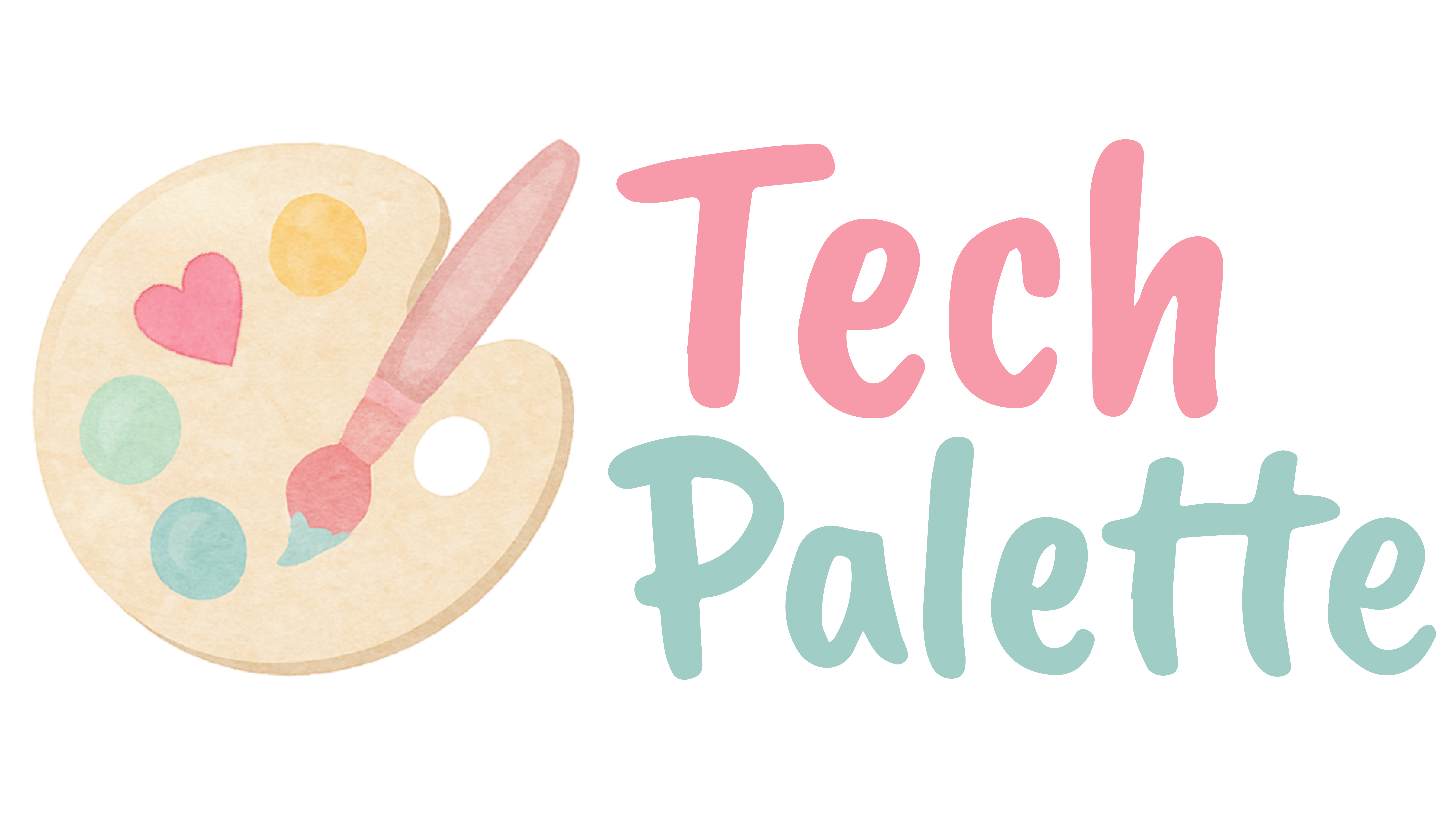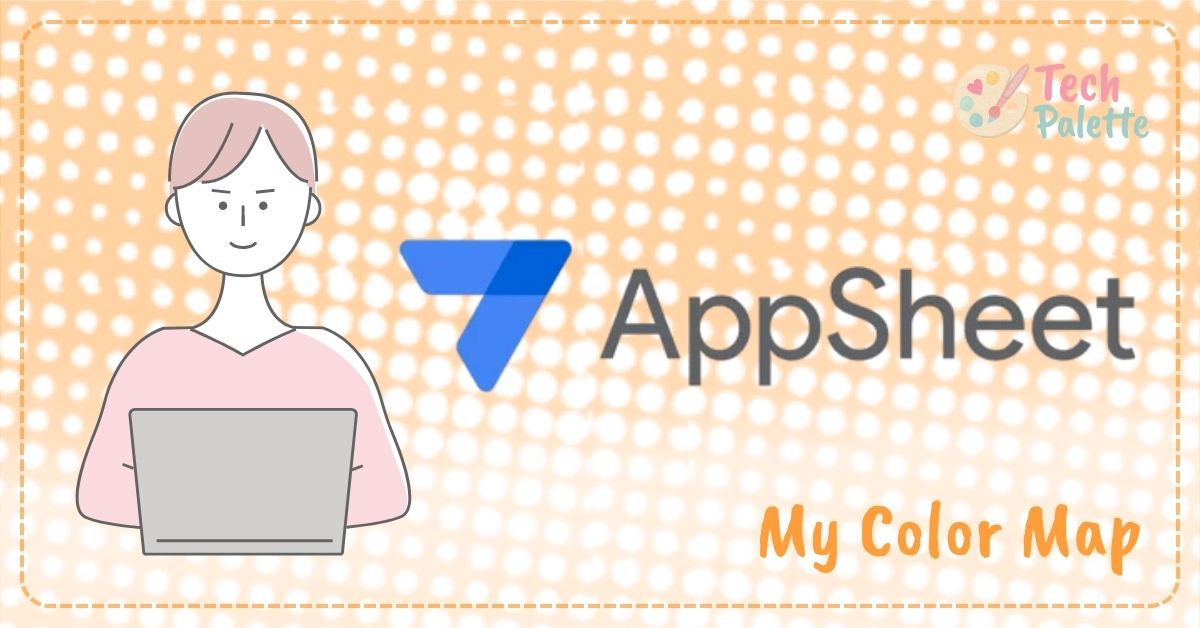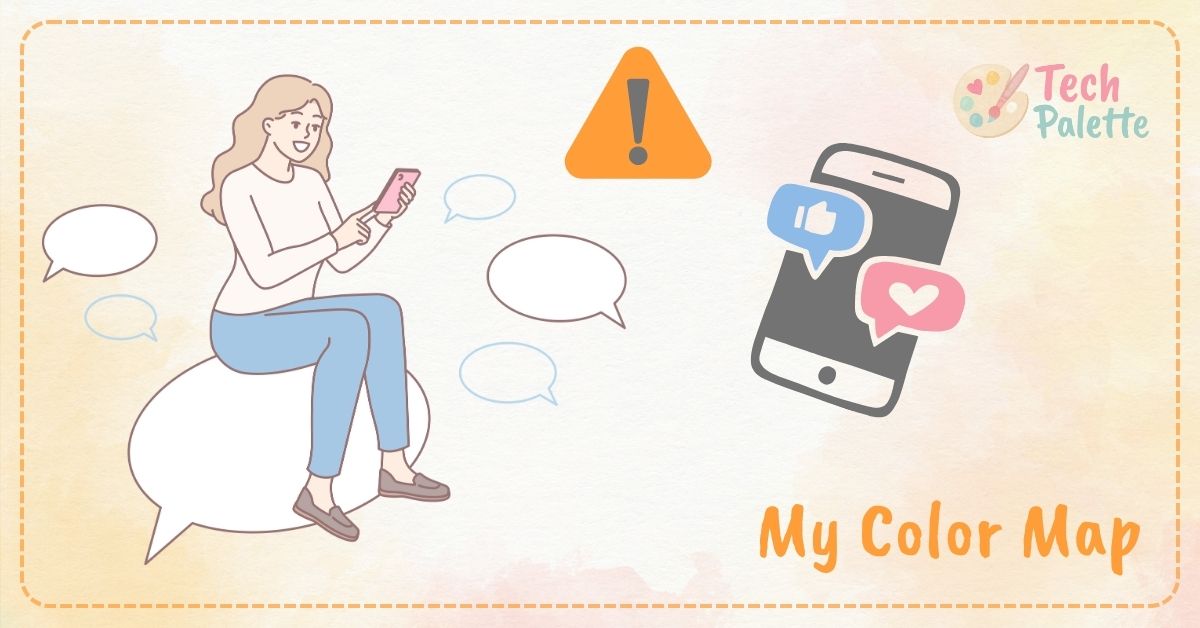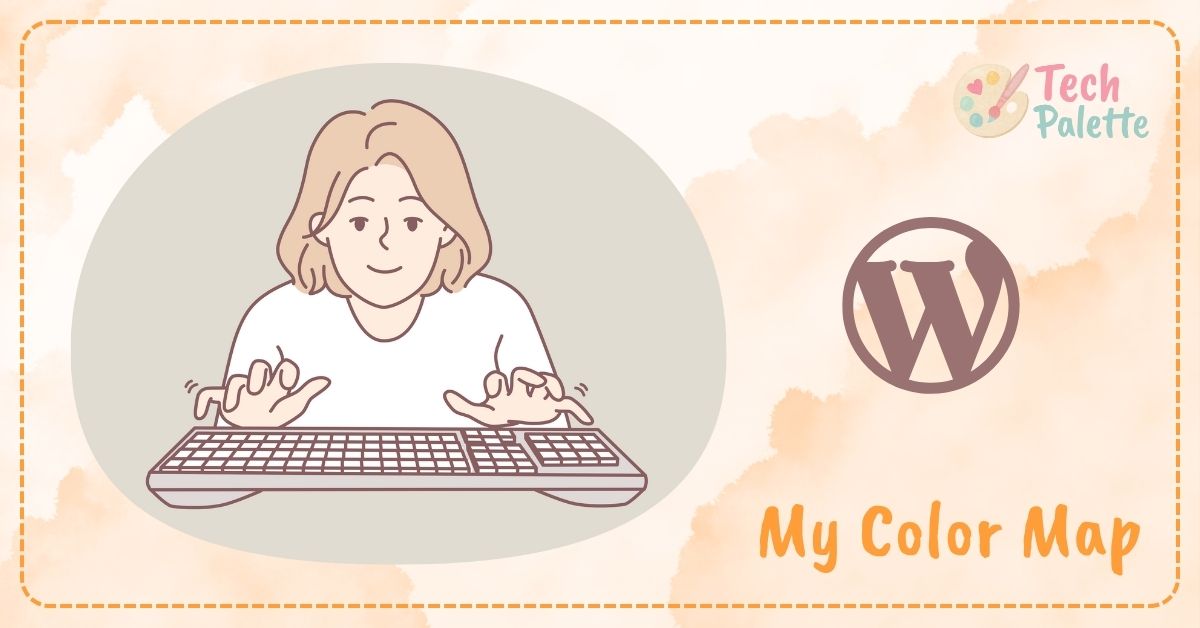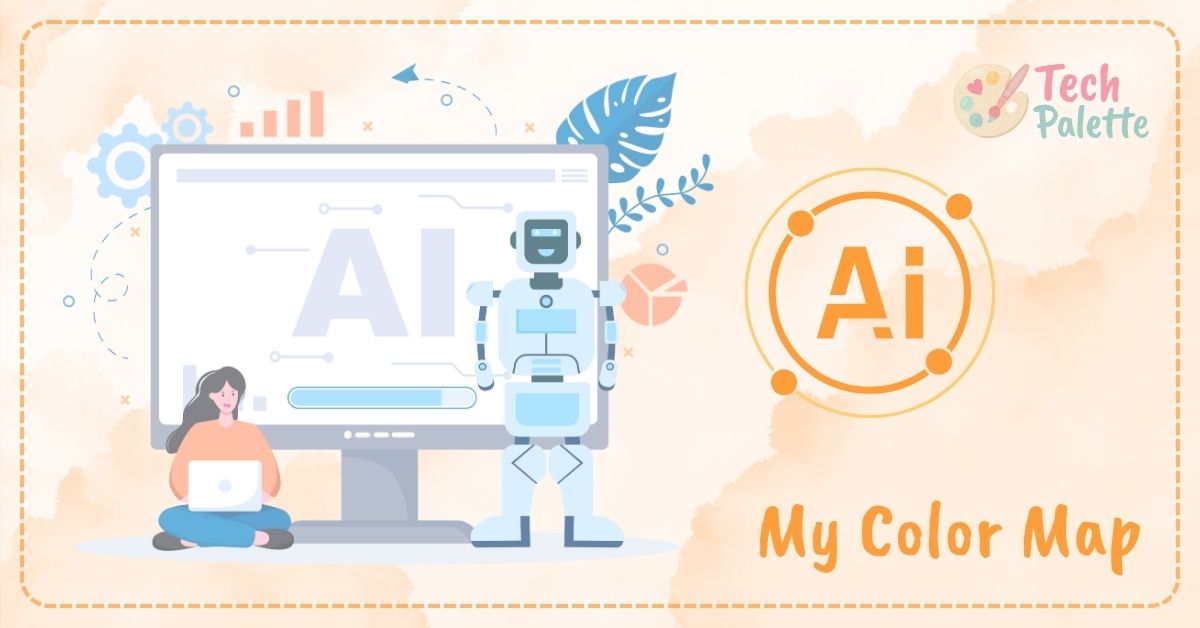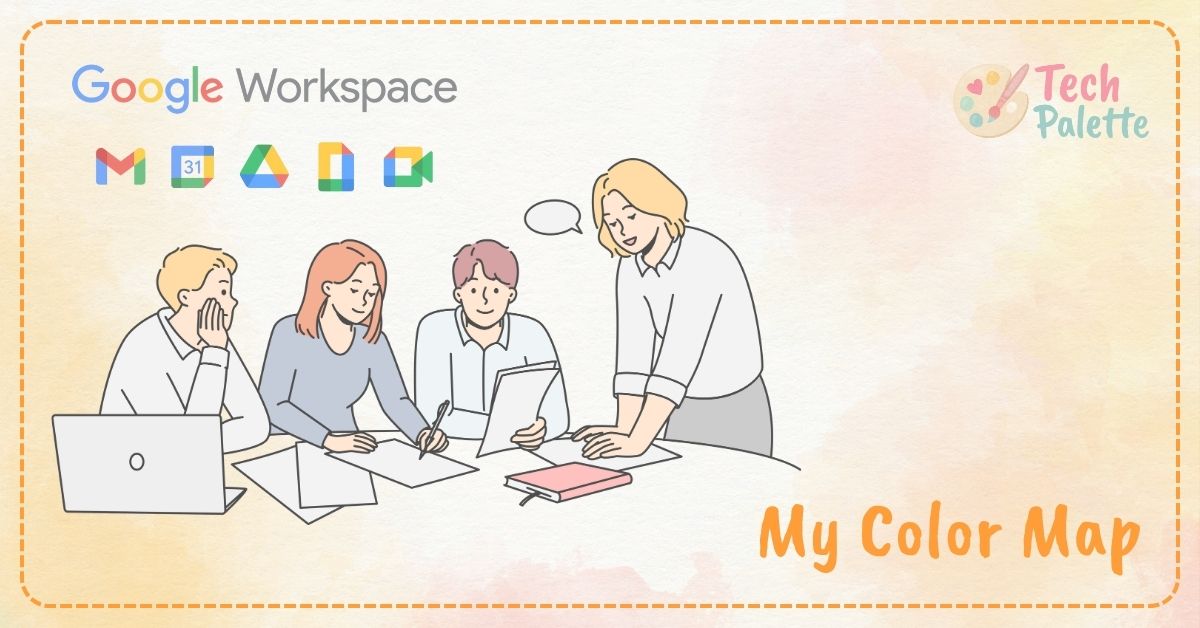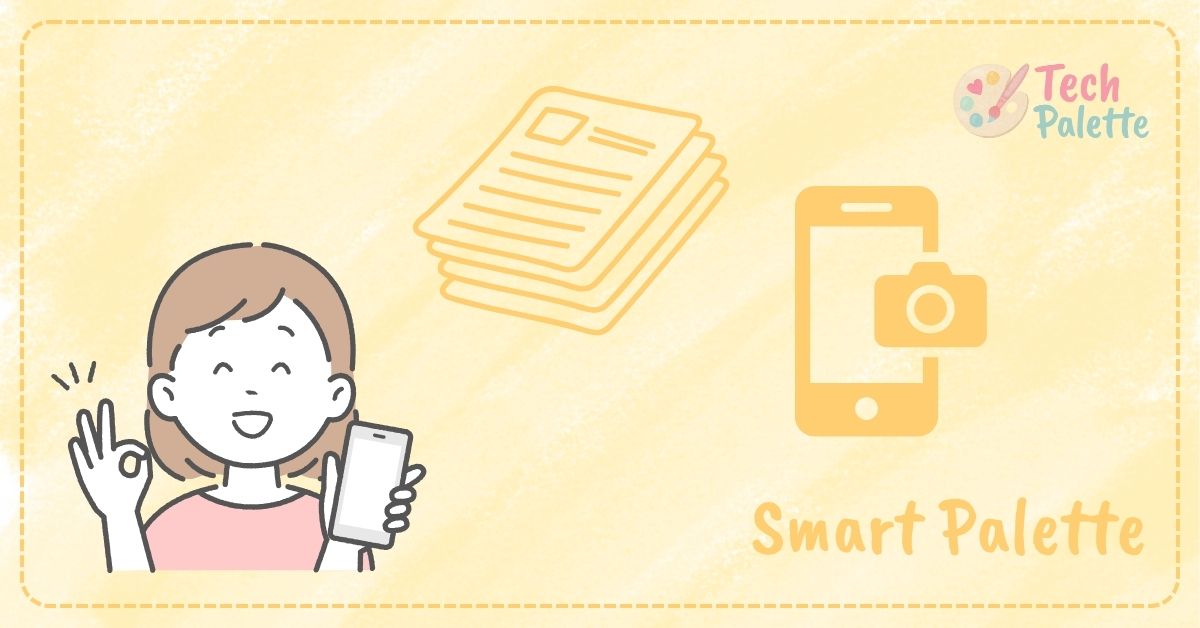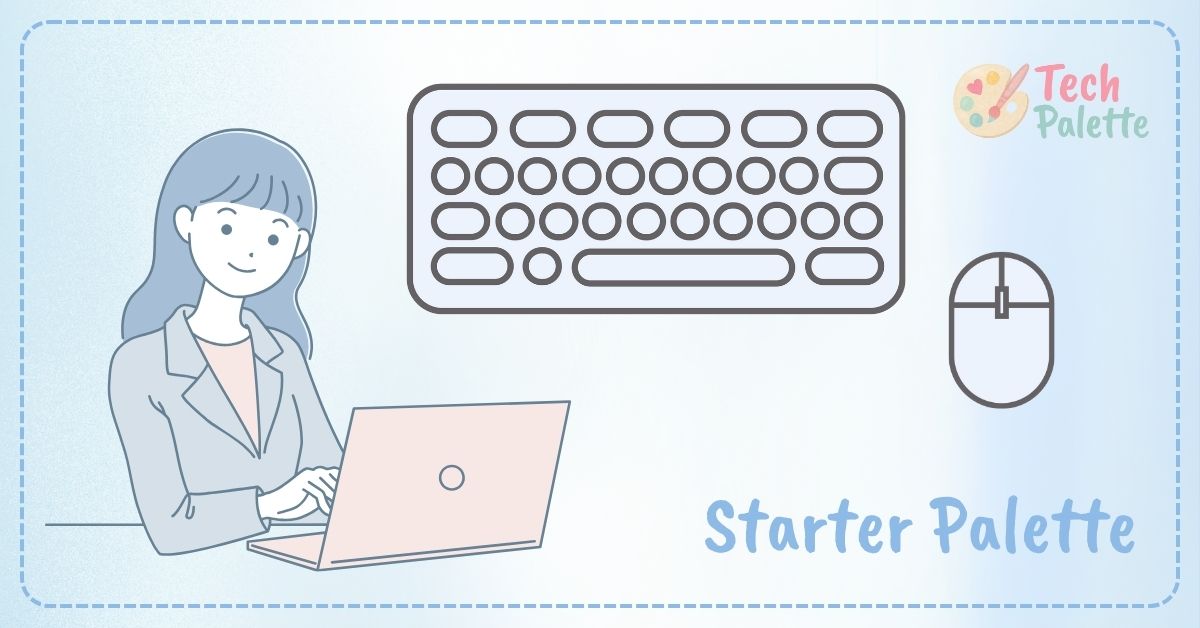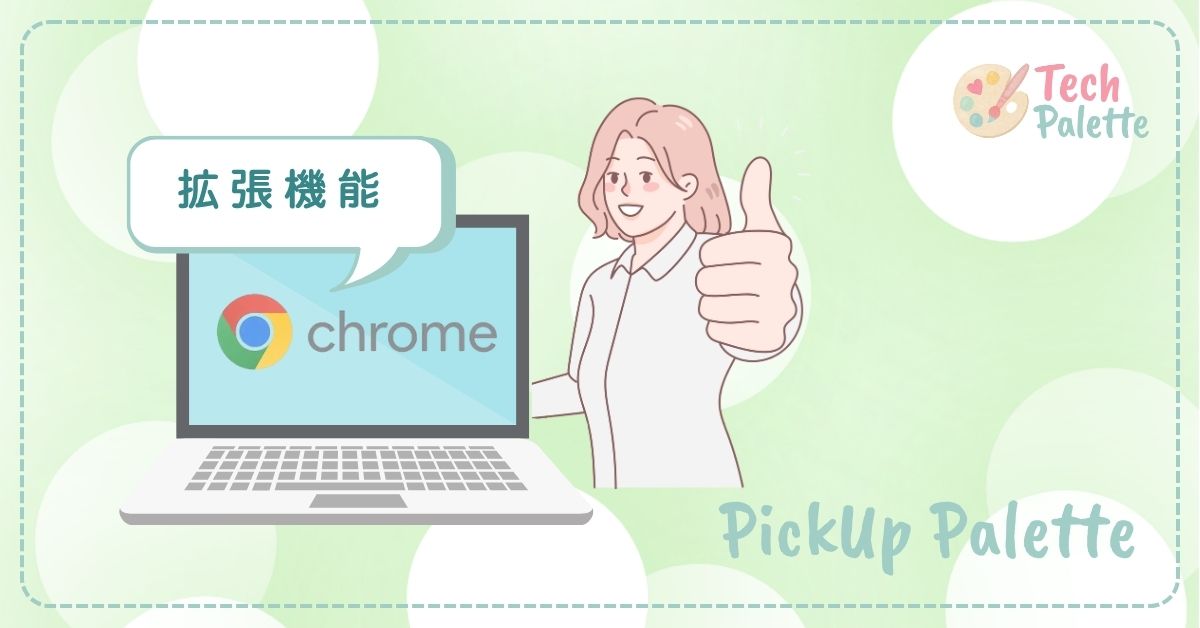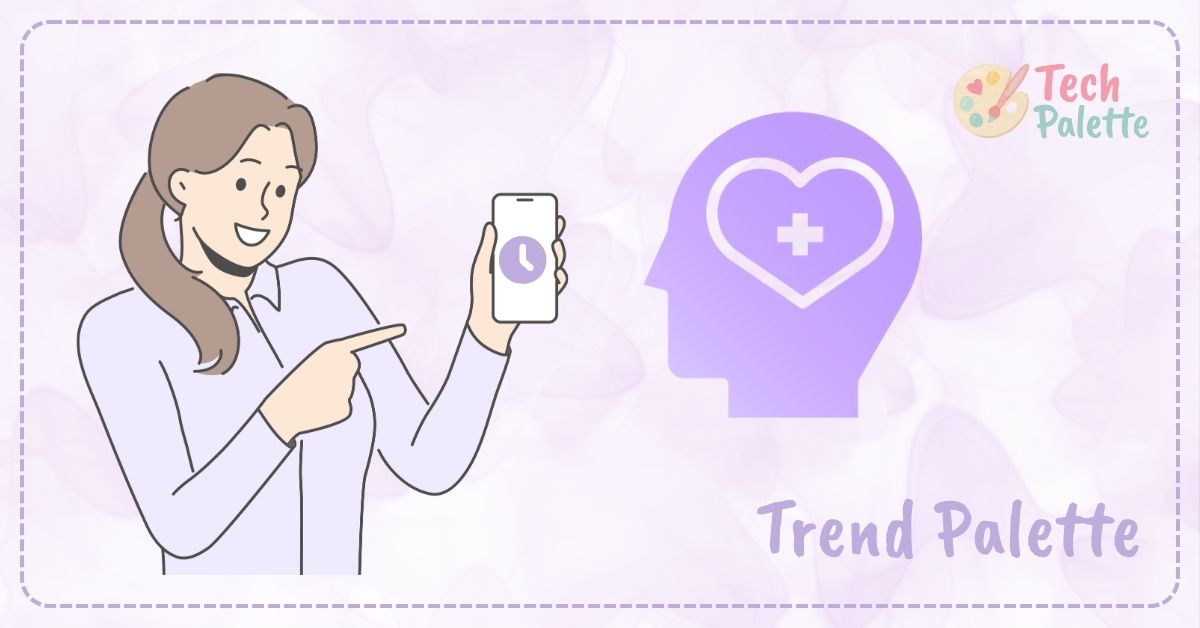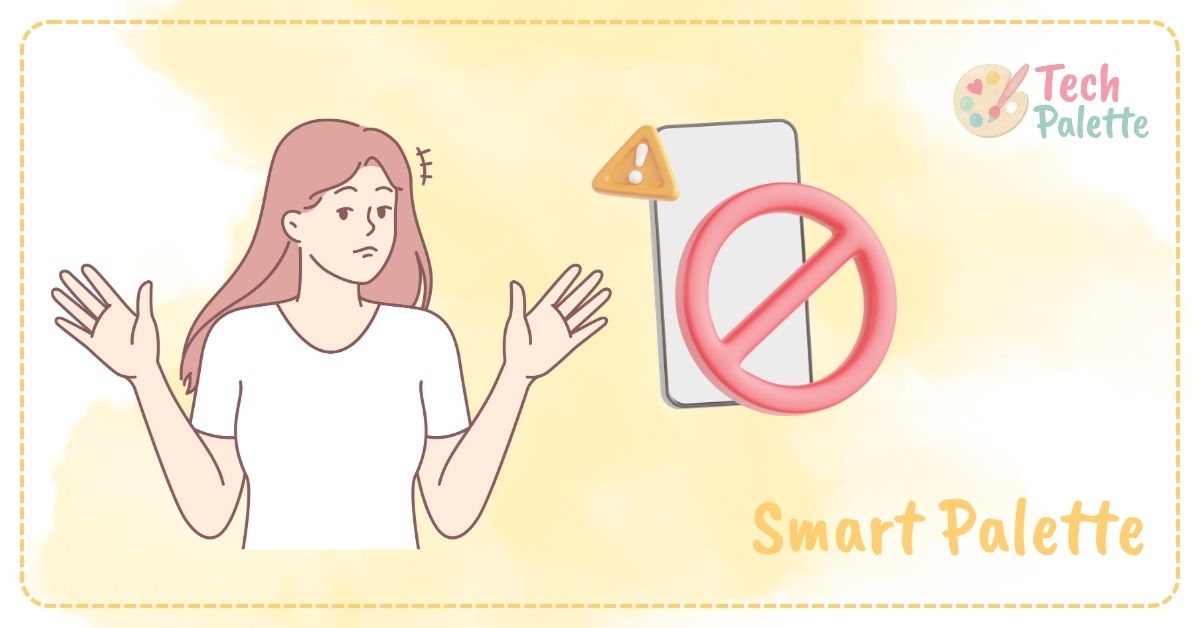AI音痴だった私が変わった日。ChatGPTとの出会いが拓いた仕事の未来
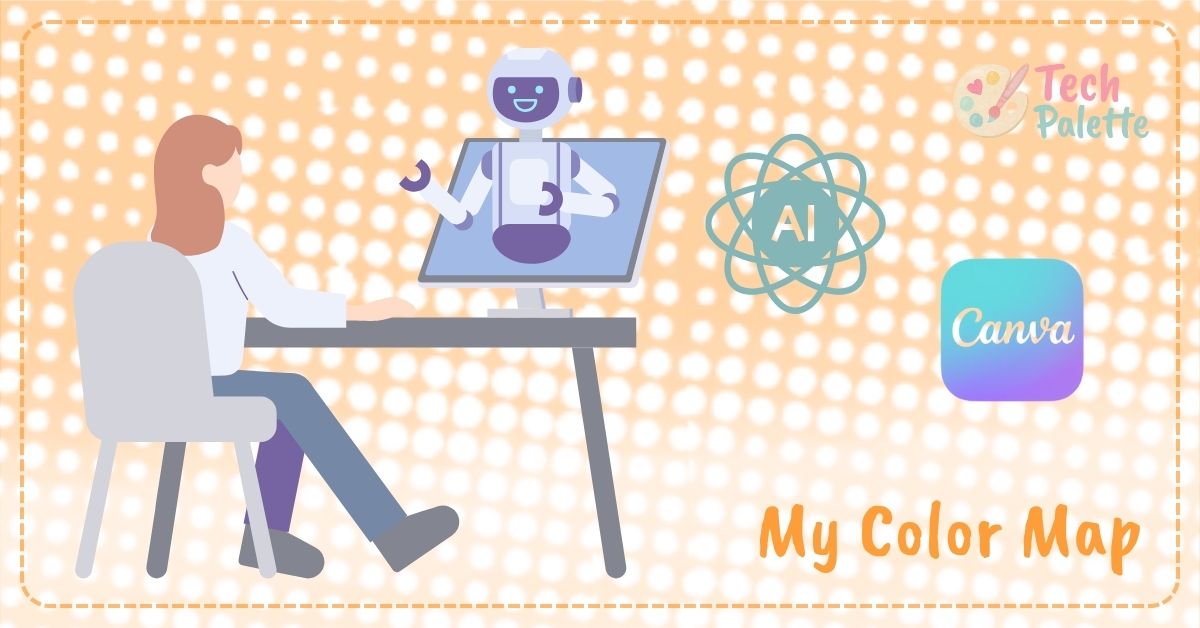
「AIは、私には無理…」ほんの少し前まで、本気でそう思っていました
「AIって難しそう」「私には関係ない話かも」
そんなふうに思っていたのが、ほんの少し前の私でした。
もともと保育士としてキャリアをスタートし、事務や介護の仕事を経て、現在は中小企業でDX推進を担当している私。
今でこそAIやWebデザインに触れる毎日ですが、キャリアの始まりはテクノロジーとは無縁の世界でした。
この記事では、そんなAI音痴だった私が、ひょんなことからChatGPTと出会い、仕事への向き合い方や未来への考え方が大きく変わったリアルな体験談をお話しします。
もしあなたが、AIに対して少しでも苦手意識や不安を感じているなら、ぜひ最後まで読んでみてください。
「私にもできるかも」と、新しい一歩を踏み出すきっかけになれたら嬉しいです。
AIって、なんだか遠い世界の話だと思っていませんか?
テクノロジーとは無縁だった私
振り返れば、私のキャリアは「人」と向き合う仕事が中心でした。
保育士として子どもたちの成長を見守り、介護の現場では利用者さまの心に寄り添う。
パソコンは事務仕事で使うけれど、それはあくまで業務をこなすための「道具」。
Excelでマクロを組んで業務効率化に夢中になった時期もありましたが、それはあくまで与えられた業務の中での工夫でした。
「AI」や「システム開発」なんて言葉は、ニュースで見るくらい。
自社でAIを搭載したシステムを開発していると聞いても、「すごいなぁ」と思うだけで、その仕組みや可能性について深く考えようとはしませんでした。
正直に言うと、「難しそうだし、私には関係ない」と、無意識に壁を作っていたのかもしれません。
きっかけは突然の「社内プレゼン」
そんな私に転機が訪れたのは、本当に突然のことでした。
会社が、既存のAIシステムに「生成AI」を新たに搭載するプロジェクトを立ち上げることになったのです。
そして、なんと「全社員が、その新システムに関するアイデアをプレゼンするように」というお達しが…!
デザインやデータ整理で少しだけ関わってはいたものの、システムの仕組みについては全くの素人。
「え、私がアイデアなんて出せるわけない…」と頭が真っ白になりました。
でも、考えてみてください。
触ったこともないものについて、アイデアなんて出るはずがありませんよね。
腹をくくって、「まずは、その“生成AI”とやらがどんなものなのか、自分の手で触れてみるしかない」と決意したのです。
これが、私のAI活用への、小さくも大きな第一歩でした。
知識ゼロからの挑戦!イベント参加と初めてのChatGPT
「世の中はこんなに進んでいるんだ…」展示会で受けた衝撃
社内プレゼンが発表される少し前、2023年12月に開催された「第14回コンテンツ東京」という大きなイベントに、社内の皆で見学に行く機会がありました。
会場を歩いてみて、本当に驚きました。
クリエイティブ、ライセンス、映像、広告、そして最先端のデジタル技術…。
あらゆるブースで「生成AI」という言葉が飛び交い、AIを内部に組み込んだシステムが当たり前のように展示されていたのです。
「こんなにも世界が進化していたなんて…」
そのとき感じた衝撃は、今も鮮明に記憶に残っています。
自分が「難しそう」と敬遠している間に、世界はどんどん新しいステージに進んでいる。
このままじゃいけない、という焦りに似た気持ちと、新しい世界への好奇心が、私の心の中で同時に膨らんでいくのを感じました。
まるでLINE?おそるおそる触れた生成AIの世界
イベントで刺激を受け、社内プレゼンという目標もできた私。
いよいよ、話題のChatGPTに触れてみることにしました。
とはいえ、知識はほとんどゼロ。
「LINEみたいに、AIとチャットするサービスらしい」くらいの認識です。
おそるおそるアカウントを登録し、画面を開いてみました。
シンプルな入力ボックスがひとつ。
「何を話しかければいいんだろう…」 しばらく考えた末に、プレゼンのテーマに沿って「自社のシステムに生成AIを搭載するなら、どんなことができる?」と、そのまま入力してみました。
すると、どうでしょう。
数秒もたたないうちに、AIはまるでベテランのコンサルタントのように、考えられるアイデアをいくつもリストアップしてくれたのです。
- 「ユーザーの質問に対して、より自然で人間らしい対話形式で回答できます」
- 「顧客データを分析し、パーソナライズされたサービス提案を自動生成します」
- 「新しいコンテンツのアイデアを、ブレインストーミング形式で複数提案します」
驚きました。
私が一人でうんうん唸っていても出てこなかったような視点や言葉が、次々と画面に現れるのです。
これは、ただのチャットじゃない。
私の思考を整理し、広げてくれるパートナーのような存在だ、と直感しました。
ChatGPTの始め方は、ただ「話しかけてみる」こと。
本当に、それだけだったのです。
AIは「魔法の杖」じゃない。でも、最高の「パートナー」になる
アイデアの相談相手になってくれたChatGPT
それからというもの、私はプレゼン準備のために毎日ChatGPTと「対話」するようになりました。
「こんな機能はどうかな?」と投げかければ、「面白いですね!その場合、こんなメリットとデメリットが考えられます」と返してくれる。
「もっとキャッチーな表現はないかな?」と聞けば、いくつも候補を挙げてくれる。
まるで、24時間いつでも付き合ってくれる、優秀な相談相手のようでした。
AIは、私の代わりに仕事をしてくれる「魔法の杖」ではありません。
でも、私のアイデアを引き出し、多角的な視点を与え、思考を加速させてくれる「最高のパートナー」になってくれる。
そう確信したのです。
▶ 【ChatGPT(チャットジーピーティー)】を使ってみる
もう一つの挑戦。資料作成の相棒、Canvaとの出会い
実はこの時、もう一つ挑戦したことがありました。
プレゼン資料の作成に、PowerPointではなく初めてCanva(キャンバ)を使ってみることにしたのです。
きっかけは、アルバイトの女子大生から聞いた「Canvaって便利ですよ」という言葉と、社内でWebデザインツールをFigmaに切り替えたタイミングだったこと。
「これからは、もっと便利なWebツールを使いこなしたい!」という気持ちが後押しになりました。
ChatGPTが「思考のパートナー」なら、Canvaはまさに「表現のパートナー」。
直感的な操作で、自分のアイデアがどんどん伝わる形になっていくのが楽しくて、夢中で資料を仕上げました。
▶ 【Canva(キャンバ)】を使ってみる
「私にもできた!」小さな成功が、未来を拓く大きな一歩に
プレゼン本番。
私は、ChatGPTと一緒に練り上げたアイデアを、Canvaで作成した資料を使って、自分の言葉で堂々と発表することができました。
結果は、上司や同僚からも高評価。
なにより嬉しかったのは、「こういうの得意だったんだね!」と驚かれたことでした。
この「私にもできた!」という小さな成功体験は、私にとって大きな自信になりました。
「テクノロジーは難しいもの」という思い込みが、「私にも使える、面白いもの」へと変わった瞬間です。
このプレゼンをきっかけに、私のアイデアが会社のシステムに反映されることに。
さらに自信がついたことで、GPTsの作成やDifyでのフロー構築など、より高度なAI活用にも挑戦できるようになりました。
副業の案件提案でも、自信を持ってAI関連の提案ができるようになり、仕事の幅がぐんと広がったのです。
セミナー講師として、学びを共有するように
今では、社内でプロンプトエンジニアとしての業務にも携わっています。
さらに、ある案件でご一緒した際、私の生成AI活用を見た自社代表の経営者仲間の皆さまから「使い方を教えてほしい」と声をかけていただき、地元の中小企業経営者向けにChatGPT活用セミナーを開催することに。
セミナーは好評をいただき、現在は定期開催という形で継続中です。
企画、資料作成、講師まですべて自分で担当し、学びを「伝えること」へと広げる喜びを実感しています。
資料作成は、もちろんCanvaを利用して…
社内外でAIの可能性が広がっていくのを感じるたびに、「学び直し」が人生に与える力の大きさを噛みしめています。
「AI」と「Canva」、この2つの出会いが、DX推進という新しい役割に私を後押ししてくれました。
できることが増えるたびに、仕事はどんどん楽しくなっています。
AIと共に歩む、これからの「私らしい働き方」
「仕事を奪う存在」から「可能性を広げるパートナー」へ
「AIに仕事を奪われる」という言葉を、あなたも耳にしたことがあるかもしれません。
でも、私は自分の経験を通して、そうは思いません。
AIは、私たちの仕事を「奪う」のではなく、むしろ「拡張」してくれる存在です。
面倒な作業や情報収集を任せることで、私たちはもっと創造的で、人間にしかできない仕事に集中できるようになります。
保育士や介護士として「人」と向き合ってきた経験。
事務職として培った「効率化」の視点。
そして今、AIという新しいパートナーを得たこと。
これまでのキャリアが、一本の線で繋がったような気がしています。
文系出身だから、テクノロジーは苦手だからと諦める必要は全くありません。
むしろ、多様な経験を持つ人こそ、AIとユニークな化学反応を起こせる可能性を秘めているのです。
あなただけの「テクノロジーパレット」を見つけよう
このブログ「Tech Palette」は、絵の具のパレットに好きな色を足していくように、あなたらしいテクノロジーとの付き合い方を見つけてほしい、という想いで名付けました。
AI、Webデザイン、SaaS、ノーコード…。
たくさんの「色(ツール)」があります。
大切なのは、すべての色を使いこなすことではありません。
自分に合った色を選び、暮らしや仕事に彩りを加えていく。
そんな“あなただけのテクノロジーパレット”を描いていきましょう。
キャリアチェンジを考えている女性も、日々の業務をもっと楽にしたいと感じている方も、ぜひ小さな一歩から始めてみませんか?
【まとめ】AI音痴だった私が変わった日。大切なのは「まず、触れてみること」
ほんの少し前までAI音痴だった私が、今では仕事のパートナーとしてAIを活用できるようになりました。
そのきっかけは、たった一つの「触れてみよう」という好奇心と、小さな必要性でした。
この記事を読んで、少しでも「AI、試してみようかな」と思っていただけたなら、こんなに嬉しいことはありません。
1.苦手意識は一旦忘れて、まずは触れてみる。
2.完璧を目指さず、簡単な質問から話しかけてみる。
3.仕事の「相棒」として、相談相手になってもらう。
大切なのは、この3つのステップです。
ChatGPTの始め方は、あなたが思うよりずっと簡単。
あなたらしい働き方、あなたらしい未来を彩る新しい「色」が、そこにはきっと待っています。
一緒に、テクノロジーを味方につけて、自分らしいパレットを広げていきましょう。
関連記事:【初心者必見】ChatGPTの始め方とおすすめプロンプト活用術|今すぐ使える無料ツールも紹介!
関連記事:【初心者向け】文章が苦手でも大丈夫!ChatGPTは“言葉にできない”を助けてくれる心強いツール
関連記事:【初心者向け】Canvaで「伝わる提案書」をサクッと作る4ステップ — 無料プランと有料プランの違いも徹底解説!